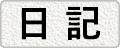
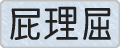



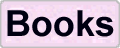

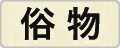
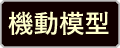



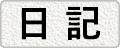
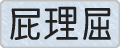



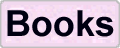

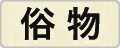
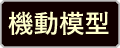



|
屁理屈 Kaikou. 世界の、ひみつ大概の皆さんは薄々お気づきのことと思うが、この世界には秘密がある。もっとも万物一如という言葉が知られているくらいだから、存外よく知られた秘密ではある。それはこの世界が、人間の見たままのものではない、ということだ。 人間に認識される世界の形態は、人間の認識形式の機能した結果であって、世界それ自体が、人間の見ているように、聞いているように、嗅いでいるように、そしてそうだと思っているようにそのまま存在するわけではないのだ。人間の認識を離れたところでは、世界は人間が見ているようなカタチを、たぶんしていない。 もっとも、人間は人間の認識能力を離れて世界を認識することは出来ないので、これは確かめようがないから、たぶん、としかいえない。(それこそ、この文章が「屁理屈 Kaikou.」である所以なのだ)だから、戯言と思っていただいてもよい。 だが、考えてみるなら、これは簡単に知れることである。 考えてみよう。我々は自分たちの認識を世界だと思っているが、その認識をしているのは我々自身の認識能力なのであるから、考えるべきもっとも重要なことは、「人間の認識能力は信用できるのか」だ。 ここでいう認識能力とは五感とその処理の能力のことである。たとえば人間の目玉は水晶体である。ほとんどの電磁波を通過させる。よって目玉は、世界に飛び交う電磁波のほとんどを「視て」いる。しかし、目玉の奥にある視神経の光センサーは、特定の周波数にしか反応しない(可視光線、というヤツである)。この反応の脳内で立体画像に処理されたものが、心によって「視える」世界である(情報処理をするものが脳だけなら、映像が見える必要はない)。この視える世界には、X線や遠赤外線、電波は映らない。映像はつまるところ電磁波の反射が像を結んだものであるから、もし人間の目にこれらの周波数が見えたなら、人間の視る世界にはもっと多様な映像が映っていることだろう。測定機械の発明によって人間はこれらの電磁波のあることを知ったが(ある意味でそれは発見したというより開発したというべきなのだろう)、もしその経験がなかりせば、人間は永久に、それらの電磁波があることを知らなかったろう。当然、それらが人間の目には見えていないことも、知りはしなかったにちがいない。だが、それらはある。人間の目は、すべての世界の映像(電磁波の反射)を映しているわけではないのだ。見えないものが、この世界にはある。もうそれだけで、世界は視たままのものなどではないことが知れる。
同じことは、聴覚、嗅覚、触覚、その他もろもろにも言える。(ある人によると、人間には霊感もあるのだそうだが、とりあえずそれも含めておく)聴覚は空気の振動波のある強さを切り取った認識に過ぎないし、嗅覚もある特定種類の化学物質に対する反応、触覚もある強さ以上の圧力感知による、神経の信号発信に過ぎない。人間の認識能力には、あらかじめ認識器官の性能特性によるフィルターが掛けられているのだ。脳内での情報処理の結果認識される「世界」は、そういう切り取ってきた情報を総合したものに他ならない。つまるところ、人間にとって、世界は人間の認識能力の限界(器官の特性)に依存して描き出される、器官(とその持ち主)に依存した主観的なものなのである。 たったいまするりと書いてしまったが、さらに、この認識は人間個人の認識能力に(もちろん)依存している。たとえばあなたが視ている、聴いている世界は、あなたの認識能力が収集した情報を総合したものだ。あまりいい喩えではないが、もしあなたが言葉の意味通りの赤緑色色盲で、赤い色がどれもみな一様に緑色に見えるとしたら、あなたは、赤という色を現実の世界の要素として認めることは出来ないだろう。たとえ他人が口を揃えて赤い色はちゃんと在るんだ、と主張したところで、あなたの世界に赤い色は(現実として)「存在しない」。したがって、この場合あなたの世界は赤い色のない世界が「現実」であり「真実」となる。いや、それは例外であって 、みんなが認識しているものなら、それは個人の認識能力の特徴に関わらず在るのだ、というのなら、その人はガンマ線が見えるとでもいうのだろうか。多くの人に認識されるものなら在る、と主張することは、逆に言えば、多くの人に見えないものはない、と主張することに他ならない。では、多くの人には(っていうかすべての人には)見えないガンマ線は、当然ないはずなのだが、在るんでしょう?(機械によれば) ただ話を混乱させているだけのような気がしてきたが、もう少し混乱させてみよう。脳にある種の傷を受けた人は、特定のものを認識できなくなったり、特定の行動をとることが出来なくなったりする。架空の例だが、「杖」という概念を理解していても、杖だけは識別できない、といった場合だ。この例なら、目の前に杖があっても、その人は杖があることを決して認めることが出来ないだろう。そして、その人にとっては、そうした「杖のない世界」こそが現実世界である。 いや、それはその人の脳に異常があるだけだ、脳の誤動作の結果であって、一般的な脳は正確に世界を認識している、ともしいう人がいるならば、その人は、自分の脳が認識した情報を正確に処理しているなどと、どうしていうことが出来るのか(いや、いえはしない←反語表現)。 人間の認識する世界は、五感の機能特性と、脳の情報処理特性(受容した情報を処理するしかた)に完全に依存している。そして、混乱する例をもう一つ。 科学に拠れば、およそ世界のものはみな粒子で出来ているのだという。ものは分子の固まりで、分子は原子と電子の結合物で、それらはまた素粒子の結合物で、というように(素粒子にはクォークという名前があり、数々の種類や構造が発見されているが、粒子と呼ぶことさえためらうほどこの定義は最近あまりに多様なので、単にひっくるめて素粒子と呼ぶことにする)。マクロなところに限って話を進めるが、つまりあなたの身体は分子で出来ており、空気も分子で出来ており、あなたの前の机も分子で出来ているとこういうわけだ。分子の違いは構成するさらに細かい粒子の組み合わせの違いで、つまるところはどれもクォークの構成パターンの違いによって区別される。したがって「あなた」と「空気」と「机」は、それを構成する粒子のパターンの違いによって区別されるものであり、ついでに、人間の感覚器官(視覚、触覚)によって区別されるものである。あなたはあなたという自覚によって、机は目に見え、触ると堅いモノとして、空気はその間の何もない部分として。さて、では、これらはいったい、別のモノなのだろうか。 また変なことをいうと思われるかも知れないが、要はある特定種類の粒子の、組み合わせの違いによってそのものの物理的な状態が違い、それが人間の感覚器官のセンサーによって別のモノとして認識される、とこういうことでしょう? 視覚は物質の構成粒子の違いによって生じる電磁波の反射率の違いによってモノとモノを区別し、触覚は感圧の違いによってモノとモノを区別する。そしてそれらの違いの由来は、構成する粒子の差であると。(ついでにいうと、その粒子の種類は特定の範囲内に収まる) それならば、それらのモノの違いは、同じ「粒子」の、「繋がり方の違い」であると、どうしていっていけないだろうか。 無論のこと、いけなくはないのだ。それらは同じモノである。単にそれを、性質の違いからくる、感覚器に達する情報の違いによって、人間の感覚器官が差異として認識し、脳が別のモノとしてその情報を処理する、というだけの話である。 脳が差異として与えられた情報を別のモノとして処理する、というのは、「別の名前を付ける」ということである。(結果論だが)感覚器から受ける方法の差異に、名前を付けて区別するという処理を施すことで、われわれはそれらを別のモノとして認識し、理解するのである。
だがいうまでもなく、それは認識の内側のことでしかない。 認識のその構造を取っ払った処に、世界がどんなものとして映るのかは、我々人間には確証できない永遠の謎である。だが、少なくとも、認識している「世界内部の事物の違い」、世界にはいろいろなモノがあって、それらは別のモノであるという、子供でもわきまえているようなことが、「事実ではない」ことだけは間違いない。(真実という言葉は使わない。真実も事実を、区別する必要はない) では、世界の「事実」はどんなものかというと、これは悲しいかな推論することさえ出来ない。我々人間は、推論するための「正しい情報」さえ、世界から受け取ることは出来ないのだ。人間の認識する情報が、まったくの間違いというわけではないのだが、決して正確でもないことは、いま述べてきたとおりである。では、その正確でない部分、モノに違いはない、違いは認識の結果生じる錯覚である、という部分を基準にせめて想像するならば、世界の実体は、いったいいかなるものであろうか。 世界は「存在するひとつのもの」だ。少なくとも、(われわれ自身を含めて)「なにか」が存在することだけは間違いはない。存在する、なにか。それが「世界」の、想像し得る唯一の実体であり、出来得る限り正確に表現するなら、それは「在る」だ。(動詞) せっかくだからさらにアクセルを踏もう。いわゆる一元論に聞こえるが、西洋の一元論とは少々違う。西洋思想上の一元論とは、世界は「ある一つの物質(水とか)が基になっている」とするものだが、世界は一つの物質ではない。「一者」と表現した西洋思想もあるが、世界は一者ではない。「あるもの」ですらないのである。「なにか」ですらないだろう。便宜上「世界」と読んでいるが、この世界は、実は「世界」ですらないのだ。 言葉で呼ぶ、命名する、ということは、そのものをそれ以外の何かから切り離して、一個の独立したものとして定義することである。たとえば、あるなにかを「あるなにか」と呼んで区別するなら、そこには「あるなにか」と「それ以外のもの」のふたつが出来る。しかしそうした区別が成される以前の、本来の世界は、そういう「区別できるもの」ではないのだ。「一者」と呼んでさえ、そこには一者とそれ以外が生じる。「世界」と呼んでも、世界という独立したなにものかがあるように聞こえる。だが… 世界は、名付けられるようなものではないのだ。名付けてしまえば、それはそれ以外のものを排除する。「これ」に「これ」という名前を付けることは、「あれ(これ以外のもの)」を「これ」から排除することであるように。しかし、世界には、排除されるべきなにものもない。世界は「すべて」であるからだ。言葉にしては、世界は表現できないのである。 強いて言えば、「在る」のだ。その「在る」はしかし内部に運動を持っている。運動する「在る」なのだ。その運動の結果、「在る」の内部には局地的な「差異」が生じる。分裂するのではなく、内部に運動によるエネルギーの差異のようなものが生じる。これが物事として(人間に)認識される。現象(陽が昇るとか、水が生じるとか、恒星が誕生するとか、生き物が生きるとか、便意が生じるとか)とは、この「在る」内部の運動によって生じるみかけの存在である。そして、人間の認識能力によって分別され、定義され、分類され、関係性を考え出されることによって、人間の脳内に「世界」として生じる。 これが、「世界のひみつ」である。そしてそれが実際のところ何なのかは、人間には知り得ないし、語り得ない。 これがたぶん、人間の知り得る世界の実体の限度だ。少なくとも、いまのわたしの思考能力ではこれが限界である(勉強が足りない)。 それ以上に正確に世界の実体を知り得る方法があるなら、それはたぶん「悟り」とやらをひらくのみなのだろうが、わたしはどうもこれには懐疑的である。仏教は、つまるところ「捨てろ」と命じる宗教である。極端な話、禅では「認識を捨てろ」とすらいうのだ。さすれば悟りは開かれん、と。(わたしはそのように理解している)だが、人間が、認識を捨てることが出来るものなのだろうか。しかも悟りは死ぬことではないから、認識を捨てて、なお認識しながら生きなくてはならない。それが人間に可能なことなのかどうか、わたしにははなはだ疑問なので、どうも悟りでも開こうかという気にはなれない。それは無論、同時に論理を捨てることでもあるからだ。 またこれは普通しないことであるので(禅坊主を除く)、一般的には、上に書き殴ったようなことが、世界の把握の限界であるだろう(たぶん)。 てなわけで世界のひみつはおしまい。 物足りないかもしれないが、世界とはそーゆーものなのだ。人間は、その中を、認識世界を頼りに生きる他はない。精々頑張って、できるだけ正しく物事を認識するように努めませう。たとえ、それが本質的には虚構であっても、われわれにとっては、それが事実なのだから。 2000/09/27 |
all Text written by Kaikou.