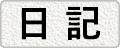
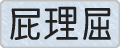



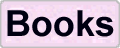

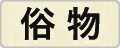
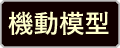



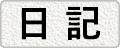
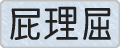



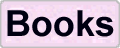

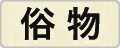
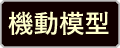



|
屁理屈 Kaikou. 気がつけばいつも日常の中余談から始めよう。 「ものごころついてから」という言葉がある。 だいたい、周囲の物事がうっすらとわかるようになってから、という意味である。逆に言うと、その頃までは「ものごころつかなかった」、周囲がうっすらとさえわかっていなかったことになる。 これは何気ない当たり前のことのように語られる言葉だが、意外に深い意味を含んでいる。 では「それまで」はどんな状態だったというのか? という疑問が、この言葉からは生じるのである。 ものごころつく、というのはぶっちゃけた話、明確な意識が生じることと解釈してよいのではないかと思うが、これはおおむね2〜3歳かそれ以降のことである。 ところが、赤ん坊を知っている人は皆知っているように、それ以前だって赤ん坊はものに興味を示したり、人見知りをしたり、オモチャや食べ物の選り好みをしたりして、ある程度、物事を識別しているように振る舞う。 では、その頃の(物心付く以前の)彼らには、ものごころはなかったのだろうか。お母さんも、お父さんも、顔を見るといつも泣き出してしまうどこぞの親戚だって識別しているのに。どうして、この頃には「ものごころついて」いないのだろうか? このことは意識が何であるのかを考えるヒントを含んでいるように思う。 同じ識別をしているのに、ものごころつく以前と以降ではなにが違うというのだろうか。識別とは、「記憶していて」、それと目の前にある事物を引き比べて同じ物かそうでないのかと判断するということである。そして良い記憶を伴った対象には良い反応を、イマイチな記憶を伴った対象にはそれなりの反応をする。つまり識別をしているのなら、記憶はしているのである。それならどうして、「ものごころつかない」時期があるのだろうか。ものごころつく前も後も記憶はあるのに、ものごころついた状態と、ついていない状態とはどう違うのか。 それは「情報の連結」ではないのか。 ものごころつく以前、赤ん坊は識別をし、個々の物事や事物をそれぞれに認識しているようである。だがそれは「個々に」、であって、それらの意味を持った(と彼らには見えている)事物は、連続した一連の物事にはなっていないようだ。 ありていにいえば、興味が(識別が)すぐに移り、常に一つ一つの識別にしか反応していないのだ。そしてそれらは目の前に、つねに、一つしかない。 そしてものごころついたとき、それらは連続した物事の連なりとなって彼らの前に立ち現れてくる。お父さんとお母さんはそこに二人でいて、床があり、床の先には廊下があり、壁があり、時折見知った人がオウチに入ってきて、外に出ると人がいて、彼らはお父さんとお母さんと同じであり、ただし両親ではない。そしてその中に、叔父さんやら近所のオバサンやらが混じっていて、お菓子やおもちゃを売っている場所があり、草のある場所と固い場所がある。 「世界」の誕生である。 そう、世界は「ものごころついて」初めて立ち現れる人工物なのだ。 そうして意識が生じると、彼らは世界に意味を与え始める。いいこと、わるいこと、おもしろいこと、つまらないこと、イヤなこと、そして「いつも周囲にあること」。 それらは彼ら「ものごころついた者達」だけの、固有の事物である。彼らの物心は、自分についてだけのものなのだから。 そして、彼らの物心が「いつも周囲にある」と認識する事物こそ、すべての人間が実際に生きている「現実の世界」である。「現実の世界」とは、その認識者の周囲にいつもある、と認識者が認識している物事の、おぼろげな全体なのである。 ものごころついて以降、そここそが彼らの生きていく舞台だ。子供時代に限らず、それは内容を変化させながら死ぬまで続く。つまり、ものごころ失せるまで。たとえ周囲の生活に変化が起きても、認識者がそれらの見知らぬ事象に「ものごころ」つけば、それは日常になる。 朝、起きるとなにがしかの事物が周囲にある。繰り返し繰り返し、記憶しているそれと似たような出来事が起こる。それらがいつも同じ場合もあるし、ころころと変わる場合もある。ときどきがらりと変わることもある。寝ると消える。毎日、毎日、それらおおむね見慣れた事物の中を、人は反応し、考え、決定し、行動する。 毎日、毎日、見慣れた、よく知った事物の中を生きている、と当事者が思っているのが日常だ。日常になったものは、当事者の中で深く悩んだり迷ったり不安に思ったりする必要のない事物になり、逆に言えば、その中をある程度安楽に生きることが出来る。広くは道の歩き方や建物の入り方、道具の使い方といった文化の基本フォーマットから、狭くは家族はじめ周囲の人間やよく出入りする建物、いつも使う道具や慣れた行動が日常になる。日常が変化しても、それは日常になる。繰り返し目の前に立ち現れて慣れた物事や出来事の中を、そこをこそ人は生きてゆく。 いやさ、そこだけを、人は生きてゆくのだ。よく知った出来事の中を、おおむね安心して、ときに自信なく。日常が平和でなかったとしても、あるいは望まない辛いものだったとしても、それは変わらない。粛として受け入れるにせよ、切り開くにせよ、打ち壊すにせよ、その中をしか人は生きてゆかない。 平和であるにせよないにせよ、食べたり寝たり、物を取ったり、特定の人に会ったりするそれは意識しない暮らしである。後述する物語との齟齬に置いて強い否定のない限りは、それは特別に意味だとか、価値だとかを意識しない暮らしだ。ちょっとイイとか、オモシロイとかこれはちょっとイヤだのといった些末な出来事はあろうが、おおむね何気なく流れていく。あるいは時にうっとおしく、厄介に思いながら、それでも繰り返し繰り返し、当然そこにあるものとして起こってゆく。まるで、なにものをも押し流すように。 環境を換えることはできても、日常の中身は人の意志が、そう強くは左右するものではない。だいたいは「そこにあるもの」として否応なくそこにあり、そこを生きる人の方が慣れてしまう。生活スタイルやグッズを換えても、日常が日常であることは大きく変わったりするものではない。家族という極近い人間の中身がごっそり変わってたとしても、いつか慣れていつもの日常がそこに生じる。 特別に安楽な身の上でもない限りは毎日やるべきコトがあり、否応なくそれらは実行されなければならず、否応なくヨイショヨイショと実行に邁進してゆく内に、日が暮れてまた朝が来る。 ものごころついた世界、である。そして、生きてゆく世界だ。ものごころついた人の、その人だけに起こる、繰り返し立ち現れる世界。その人が生きる本当の舞台。そして我々は、各人が、その中だけを生きて死んでゆく。ものごころついたその時からずっと連続している、その当事者の全世界。ものごころ失せるまで続く、その当事者と共にある世界。 形態は問わぬ。いや、問いようがない。形の決まった日常というものはなくて、まさに人それぞれである。何者もそれを否定する権利のない、当事者にとっての繰り返す世界が日常だ。どんあ形態だってあり得る。朝起きぬ日常などはざらだし、それどころかひとところにおらぬ日常だってある。騒がしい日常も、おどろくほど静かな日常もある。なかには血なまぐさい日常だってあるやも知れぬ。毎日嘆いているような、傍目にはあまり幸福とも見えぬ日常だってあるかも知れぬ。あるいは毎日浮かれ騒いでいるような、一見幸福な日常もあるかも知れぬ(それが幸福かどうかは一概に言えぬが)。 どのようなかたちであれ、ものごころついた者はその繰り返す日常の中を毎日、毎日、生きてゆく。嫌々繰り返すときもある。喜んで繰り返すときもある。飛び上がるほど嬉しいときも、がっかりする時もある。思わぬ時に、思わぬ形で、がらりと日常がその形を変える時もある。だがしかしそれも見慣れた日常に姿を変える。そして全体をならしてみると、それはおおむね見知った出来事へ対処する、その繰り返しである。どんな変化も、過ぎ去るか、あるいは慣れるかして、いつのまにか日常になる。 誰もが、その中を日々生きている。毎日、毎日、眠りから覚め、食事をし、する必要のあることを為し、する必要のないことを為し、よく知っていることに対処して、あるいは思いもかけぬことに対処して、摂取して排泄し、眠る。 そこは、本来は意味の入り込む余地のない世界である。生きているというだけならば、それだけで完結する、それ以上の意味を本来持っていない世界だ。たとえ意味のある大きな出来事が生じたとしても、毎日を暮らす内に、やがてそれは特別な意味を消失して日常に姿を変える。あるいは思い出の中に消える。日常には常に、日常以外の意味は生じない。そういうものなのだ。本来、そういうものだったのである。我々が、ただの生き物である限りでは。 無論、我々はただの生き物である。元来、それだけのものである。だが我々はしかし、それだけでは我慢の利かない、困った生き物でもあるのだ。 我々は、「これこれはこうあるべきだ」、「これこれはこうあって欲しい」、「これこれがこうあったらどんなにかいいだろう」、「そのためには、さて、どうしよう」とばかりに頭の中に「こうでありたい」物語を打ち立て、その中に自分を置いて(置いたと想定して)生きずにはおかれない、ある意味でヘンテコな生き物でもある。頭の中に打ち立てた物語の中を、生きてゆかずにいられない。 それは、元来日常ではあり得ないものである。目前に繰り返し立ち現れる事象ではないのだから。だが繰り返し頭の中に立ち現れる想定ではあるので、人は、それが日常であるかのように錯覚をする。そして、その中を繰り返し生きてゆく。いわゆる人の個性とは、この繰り返し立ち現れる日常ならぬ日常の物語のことである。その人らしさはこの物語に由来する。 勢い余ったものごころ、というところだろうか、それともそういったらば身も蓋も無さ過ぎるだろうか。人の、人故の浮ついた心というべきだろうか。ともあれ人は、誰しも心に、この日常ならぬ日常の姿を思い描いて暮らす。 我々は、毎日、この二つの日常の中を生きている。 一つは日常ではなく、日常の目指すものである。もう一つはそれと意識しないほどに見慣れた、よく知った繰り返しである。そしてこの二つは、滅多に調和しない。片方は物語なのだから、それは調和し易いものではない。その上、どうすれば調和するものなのか、知っている者はたぶんいない。だから誰もが、迷い、試し、試行錯誤して生きている。 我々の毎日が、良い意味であれ悪い意味であれ喜怒哀楽を持ち得るほどに有意味なのは、この二つの日常が調和しておらぬままに共存しているからである。もしもこの物語を放棄したならば、我々は毎日の日常をただ生きる、本来の単なる生き物に成るだろう。決して成り下がるのではなくて。だがしかし、寡聞にして、そういう人はあまり聞いたことがない。 我々は誰もが、そのようにして日常の中に日常ならぬ日常の物語を重ねて毎日を暮らしている。 毎日が、繰り返す見慣れた日常であるにもかかわらず、時に嬉しかったり、哀しかったり、辛かったり、穏やかであったりするのはそのためだ。「ものごころ」は、誰しも夢見がちなのである。 一方では、どんな形であれ繰り返し立ち現れる波のような見知った出来事の連続、日常があり、一方には、当事者自身がそこに日常的に投影する物語がある。そして物語の方は、押し寄せる現実ではなく物語なのであるから、そしてたとえ現実化しても形を変えて想定され続ける物語であるから、常に日常とはあまり相容れず(といって必ずしも相反するものではないが)、相容れぬままそう簡単に止みはしない。物語は日常にかぶさる形で、繰り返し毎日、毎日、当事者の日常に「日常と違う意味」を求めさせ続ける。 我々の毎日の暮らしは、そうして日常と、日常を揺さぶってときにば蹴りを入れたがる、当事者の想定した日常のあるべき物語とで成り立っている。その二つの間をゆらゆらと揺れ動き、あるいは揉まれ、怪我をし、物語の勝ちを得たり、負けを得たりして我々は暮らす。 毎日、毎日、そうやって我々は生きている。それこそが、ものごころついた我々の世界なのである。だから我々はいつもどこかしら歯がゆく、満足しておらず、ときに喜んだと思ったらがっかりしたりして、なにかと不調和を感じ続けて生きてゆかざるを得ない。この日常の物語と、日常との齟齬があまりに大きかった場合、日常は打ち壊すべき敵となり、その当事者の暮らしは戦いになる。日常に勇ましく打ちかかり、考え、試行錯誤して失敗し、状況の変化の兆しを捕らえてはようよう日常の姿を変える。そして日常に描いた物語と日常とが強い齟齬を生まぬほどにおおむね摺り合わされたとき、その当事者は新たなる日常の中を、やはり日常の物語と共に毎日、毎日、暮らしてゆく。苦しいなら苦しいなりの、平和なら平和なりの、毎日をやはり生きてゆく。来る日も、来る日も、日常に少し、あるいは強く物語の実現を期待しながら。 それは元来の日常世界とは微妙に異なった暮らしである。意味もなくただ目前に生じては過ぎてゆくのが、生き物本来の日常であるはずなのだから。しかし我々はそこに、投影した「そうあって欲しい」日常の物語が実現することを期待する。その中には、こともあろうに「毎日繰り返す同じ出来事の中を生きるのはイヤだ」という、まことに贅沢な、あるいは我が儘な期待も混じっている。常に変化を(多くは少しだけの変化を)欲し、といって変化が起きると慌て、苛つき、喜んだりがっかりしたりする。たとい変化を強く望んで、その変化が成り得たとしても、それは、やはり日常である。変化した日常の中を、人はやっぱり少し夢見て、毎日繰り返し生きてゆく。 それぞれの人がそれぞれの日常の中を、それぞれに期待し、喜び、不満に思い、がっかりして溜め息をつき、これらのことどもはこうあらんものかとまた物語を心に紡ぐ。そして、そんな当事者の心の中の物語にはお構いなしに、日常はどうどうと速い水の流れのように当事者を押し流してゆく。ばたばたせねば、まるで沈んでしまうようにして。 だから、人は、心の中の日常の物語と一致する間もなく押し寄せる日常の中をばたばたと立ち回って時を過ごし、陽の落ちた夜にやれやれと溜め息をつき、空いた時間に自分の物語の夢を見て暮らす。今日も、明日も、明後日も。そして、いつかものごころ失せて死ぬ。 それは、こういってはなんだが滑稽な、茶化していってみれば「バッカみた〜い」な日常である。日常に物語など投影しない、ものいわぬ動植物の皆さまから見れば、まるで阿波踊りのようなものだろう。 だが、それが我々の暮らしなのだ。 どうもいうことをきかぬ日常にアワアワと押し流されながら、日常のあるべき姿を夢見、ヨイショコラショとくんずほぐれつ苦闘の末に、まぁそれなりにはなるが、よくよく見ればさして代わり映えもせぬ日常の中で、風呂の湯に溜め息を吹きかけたりする。時に大きな変化を手にして、それがしかも自分の投影した物語にそこそこ近い形態を持ち、しめたものだと舌をなめても、気がつくとそれは相も変わらぬ日常に姿を変えて、よく見るとそう変わるものではない。 腹立ち千万、喜び千万、溜め息千万、というところか。 それは、たしかに、人が本来生きている世界ではない。人が本来生きている世界は、そんな期待と失望の意味の変化など屁とも思わぬ、味気なく変化し続ける「日常」に他ならぬ。だが、ものごころついた者は、ついでに夢を見ずにはいられず、そうして上滑りするかのように日常の中に期待を重ねて、溜め息つきつき、その二つの日常の中をこそ、来る日も来る日も、生きてゆくのである。 身も蓋もない上に救いもないので恐縮だが、日常に重ね合わされた物語が全く、完全に実現することはない。それは、本来日常の中には存在しないものなのだから。せいぜいが、部分的に幾つかが、やや実現する程度であろう。だから物語の増殖が止むことはなく、日常もまた当然止むことはなく、つかの間の喜びも、溜め息も止むことはない。物語が、日常に全く一致しているのでない限り。 本来の姿とは異なるのであれ、その是非とは無関係に、それが、我々の毎日である。どんな社会的地位にいる人も、どのような財力を持つ人も、どのような環境に置かれている人も、それは変わるところがない。誰も日常と、日常の物語のせめぎ合う中から逃れてはいない。生きている限り、ものごころある限り。 そして、それで良いのである。 それが、それこそが、我々、人間の生存形態なのだ。他のどんな動物とも、ちょっと違う。ある意味で可愛らしく、ある意味で滑稽で、ある意味哀しく、ある意味で愛おしい暮らしである。 その事自体に、決して不満を持ってはいけない。それは、ものごころ「つき過ぎ」である。誰もが、どんな人をもが、そうして生きて死んでゆくのだ。そんなことに、良否などあるはずがない。 それは、「日常」なのである。決して、決して、否定さるべきものなのではない。毎日の暮らしを否定する者は、自分の心を、殺してしまうことだろう。いまある暮らしを大事にしろと、言っているのではない。日常が変化すること自体は別に悪くない。イヤなら変化させて良い。それもまた、日常なのだから。だが、日常に押し流されながら日常に夢を見る毎日を暮らすこと自体を、悪く思ったり否定したりしてはイケナイ。特に、若く、思慮の走り出した世代にはきちんと覚えておいてもらいたい。 それがヒトなのである。 ヒトであることを悪く思ったり、否定したりしては決していけない。若い人たちには、よくわからなくとも決して忘れないでいてもらいたい。 確かにそれは滑稽で、ヤレヤレなコトで、けたたましく、思うにならず、面倒で、少々疲れることだ。必ずしも楽しくないし、同時に必ずしも辛いわけでもない。悲喜こもごもで、忙しく、流れ過ぎ去ってゆく。 それで、良いのだ。 我々は、そのような生き物なのである。そのこと自体に、是非はない。 無論、辛い日常は変えられなくてはならぬ。その人がそれを日常として受け入れているのでない限り(受け入れているのなら、それはそれでよい)。辛い日常を脱しようと苦闘する日々は、しかし、それですら日常である。努力の末に様々な形で日常が変化を遂げても、いつの日か、それが日常になる。日常が肯定し得る暮らしであり得るのなら、それはそれこそしめたものである。あいかわらず日常の物語はそれでも上滑りするので、アワアワするのに違いはないが。 我々は、日常と、日常の物語の中から逃れたりはしないのだ。ものごころある限り。それこそが、我々のものごころついた、我々の生きる世界なのだから。 そして今日も、我々は心密かに淡い期待に胸を膨らませ、溜め息つきつき、日常と、日常の物語の中をどたんばたんと生きてゆく。 それで良い。 そうでしょう? 2002/11/05 |
all Text written by Kaikou.