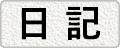
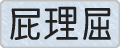



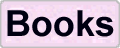

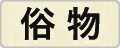
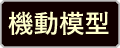



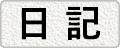
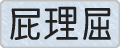



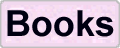

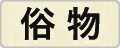
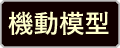



|
屁理屈 Kaikou. そこにあるもの西洋の思想には、その根底に、我々の認識能力は正しく世界の真相を把握できる、という信念が横たわっている。 もしや基督教が、人間は神のロゴスを内包した神の似姿であるという思想を広めた故ではないのかと疑っているのだが、つまりは人は神の似姿であるが故に神のこの世界に置きたまいし真理を把握可能だ、という理屈である。 わたしには、どうもこの話がうさんくさく聞こえてならない。 わたしが基督者でないせいもあるだろうが、この世界に真理のあるかどうかも判別できぬ身では、うさんくさく聞こえるのもやむなしというところである。 だから自分で考えるしかない。 考えてみるに、わたしに言い得るのは「なにかある」のは間違いない、という程度であるのがわかって、わたしは大層がっかりしている。 だがまぁ、わたしの落胆などどうでもよろしい。わたしにそれしか言えぬのなら、わたしにとって確信し得るのはその程度なのだと覚悟する他はない。 なにしろわたしは、人間の視覚、聴覚、嗅覚、触覚のすべてが、正確に世界の真相を把握しているのかどうかすら、自信を持って断言できないのだからわれながら恐れ入る。だが断言できない理由はあるのだ。例えば脳に傷を負ったある種の人々は、目に見えるモノを一部だけ、把握できなくなる場合があると云う。物理的に脳の障害を負った人にはそういう非日常的な知覚の起きる例が他にもあると聞く。 すこし悪い例の出し方かも知れないが、障碍ではないが身近には緑色色盲の人の知覚という例もある。赤緑色色盲ともいうそうだが、赤と緑色の区別がない人たちである。どちらかの色が、どちらか一方に統一されて見えるのだそうだ。赤色が緑色に見える人は、世の中に赤色を発見することができない。その人にとって、赤という色は存在しないのだ。赤い物を指して、いくら他人から赤い赤いといわれても、緑とどう違うのか、その人にはわからないだろう。 (この表現に気分を害された方がいたら謝罪申し上げる。決して誹謗する気はない) すると他の人にとっては赤は存在する色になり、その人にとっては存在しない色になる。そんなあやふやなものが「存在する」と言えるのだろうか。 同じく先の例で見える物の一部が認識できない人にとって、見えない物は存在するとは信じられないが、他の人たちはこぞって存在するのだというだろう。触ってみるとわかるのかもしれないが、そうしたら今度は、その人は自分の視覚を信用できなくなる。目に見える物は存在するのだろうか? 少なくともその人にとっては、然りとは答えられなくなる。 では、ひどい言い方だがその人たちだけが異常で、そうでない人たちにとっての認識、つまり大多数の認識は正確で正しいのだが、たまたまその人たちだけが正確に把握できないだけなのだ、とは言い得るだろうか。 無論、そうではない。それはその異常と言われる人々だけが正確で、その他大多数の人たちが、揃いも揃って異常なだけかも知れないのだから! 彼らが正確であると、いったい誰が保証するのか。多数決の論理か? それとも神か? さらに正確さを保証するその保証が正確であると、いったい誰が保証し得るのか。 我々は、認識の正確さを保証し得るだろうか? できないのだ。我々には。 認識の正確さを保証するどのような物差しも、その物差しが正確であることを保証はしない。間違いないという判断が間違いでない根拠を保証するものは、この世にはない。 だからそれは信仰である。我々は正確に世界を認識していると信仰するとき、我々の認識は正確になる。だが、我々とは誰だろう。先の例の彼らは、我々の内に入らないとでもいうのだろうか。 無論、そんなことはない。一人でも例外がいるならば、人間の認識は客観的に正しくなどあり得ない。いやさ一人の例外もなかったとしても、人の認識を客観的に保証などできはせぬ。 五感で認識する我々の、その五感の、いったいどこが客観的か。人によって異なるような普遍的でないものの、どこが客観たり得るか。あるいは誰もがそう感じる普遍的な認識ならば、それは客観なのか。誰もがそう感じるにせよ、およそそれが認識であるのなら・・。 まさしくそれは、主観ではないか。単に複数あるだけの。 複数の人間に共通する主観のことを客観という、といわれるならば、あぁそうなんですか、で終わってしまうが。しかしそうなら、先の話のごとく、客観というものも、ずいぶんたかが知れているではないか。 と、まぁ、そんなことは少し考えれば誰にでもわかることなのでくだくだしく書くのもなんだが、そんなわけでわたしには五感すら正確な世界像を把握しているとは思えない。していないと断言するだけの根拠も持たない。偏って把握している、とは言い得るかも知れないけれども、そのような認識能力が、いったい、この世界の生成変化する法則性を(それがあったとして)、正しく把握などできるものだろうか? 偏った情報から判断した法則性が、はたして真に正しいなどと言い得るだろうか。 たしかに、我々は科学という観測技術を持っている。そして、科学の観測技術から導き出された法則性は、たしかにこの世に再現可能なものである。 例えば車のエンジンがそうだ。身近な例だが、あれは科学の発見した法則性に乗っ取って作られ、法則通りの現象が実際に生じることで稼動している。 だから科学の発見した法則性は確かに再現可能であり、現実に合っているように思える。 わたしには、これが昔から不思議でしようがなかった。 実を言うと、わたしは数学というものを信用していないのである。 数を信用していない、といったほうが正しいかも知れない。数を数えるという行為が、どうして現実を反映し得るのか、わたしには長いことこれも不思議でならなかったくらいだ。 考えてみて欲しい。数を数えて計算することが現実に一致するのならば、数が存在していなくてはならない。数を数えること自体が、現実と一致していなくてはならないのだ。ならば、数は現実なのだろうか? たかが人間の認識能力を基にした抽象概念ごときが? なんだか古代ギリシャのソフィストのようなことを云っているが、実際問題、数がどこに存在しているというのだろうか。 一つ、二つ、三つ。一つと二つを足すと三つ。 だが、「一つ」とはなんだ? 「足す」とはなんだ? 「三つ」なんてものが、いったい、どこに在るだろうか? 数えるとはどういうことなのか? 数えた数字は、はたして現実なのか? だが、数を数えて、量にして、計って足して、あるいは引いて作った法則は(そこまでは数の概念の範囲内だが)再現可能で、そして技術になったとき、実際に作った機械はちゃんと稼動するのである。クルマがそうだ(別に他の機械でもいいが)。 それでは、数は存在するのだろうか。 そんなことはない。 あからさまに科学の大前提に反旗を翻すようで恐縮だが、数など頭の中にしか存在しない。リンゴが二つあったなら、それはリンゴとリンゴで、リンゴが17000あったなら、それはリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴとリンゴと以下省略だ。 ではなぜ機械は動くのか? 世界に数字が実在して、数理が実在するとでもいうのだろうか? 矛盾だ。わたしにはこれがどうも不思議でしようがなかったのだが、ある日こう考えることでなんとなく納得がいった。 確かに、この世にはなんらかの変化する運動が存在する。そしてそれは、確かに、なんらかの原理に従っている。ただし、それは数の原理ではない。しかし、我々は、科学と数学の法則が成立するような形で、その運動する世界を認識するのだ。そのように、あらかじめ我々が認識するのである。我々は、数と法則をあらかじめ内包した形に変形して、世界を認識する。数は、我々の認識能力の特性が生み出した「認識世界」の産物なのだ。 そう考えると、納得がいくことはいく。 数と法則が成立するような形で我々が世界認識をするから、我々はその中に数を見出し、数と数の間に法則性を「発見」する。気づかなかったことを、わざわざ考える形で発見するのだ。 そして、我々はそのような形でしか世界を認識できない、とするならばどうだ。 数が実在しないとしても、数の仕組みをあらかじめ含んだ法則性を持つ認識力をしか、我々が備えていないとしたら? そう、我々が、法則性の見いだせるような形でしか世界を認識していないとしたら? 我々の認識能力が選び取り、法則性を持った処理の仕方で脳が情報を処理するとき、そこに法則性が生まれるのは、当然ではないか? そしてもちろん、その場合、そう認識した世界こそが我々にとって唯一の実在世界なのだから、科学はかなり高い再現性を獲得し得る。 我々の観る世界は、そこに数理性と科学性を内包した認識能力によって観測されるのだから、常に必ず数理的に還元可能で、科学的に理解することが出来る。そうなるしかないのだ。 ただし絶対ではあり得ない。法則は、その場合でも必ず万能ではない。数が実在のものでない限り、永遠無限に、どこか間違っているからである。 牽強付会が形になったような考え方だが、そう考えることも可能だ。 そうした数と数学の法則性が実は世界の一面にしかなく、その法則性が適用し得る面をしか、我々が認識していないとしたら? そう考えるのはわたしの性格が悪く、前述の通り数学と科学という、正しいとしか思われない学問をすら、絶対などとは思っていないからである。 高等数学の世界には「空白の定理」と呼ばれるものがあるそうで、定理は正しいが、どうして正しいのか証明できない、というあからさまに怪しい一面が数学にはあるからだ。 証明できない定理が定理足り得る、証明が絶対の学問が、どうして真実足り得るだろうか。 もちろん、世界にはなんらかの変化する運動がある。確かにある。しかし、それが完全に数学的に記述可能な、言い換えれば実体としても数的なものだと考えるのは、やはり誤りだと思うのだ。 逆にいえば、認識能力が正しく正解を把握していると見なさないわたしのような立場から、どうして数を信用できるだろうか。わたしは要するに、我々の認識や考えなど、わたしのそれを含めて所詮皆、釈迦の掌の上の孫悟空ではないかと思っているのである。 わたしはそうした不信の世界を静かに生きているので、世を席巻する科学すら、絶対とは思えない。そうした世界記述の仕方もある、という程度にしか思えないのだ。 我々が認識し得るのは、我々の認識能力に限定された世界の姿でしかない。それが正しくなかったとしても、我々はそのくびきからは逃れられない。だからその中に、我々自身によって記述される世界の姿は、結局、我々自身の認識と情報処理能力の性質を映す鏡でしかないのだとわたしは思っている。 我々は数学的に記述可能な、数学的法則性を発見し得る「器官と脳のからくりに沿った」フィルターを通した、認識世界の中をのみ生きており、真の世界など生きてはいないと思うのだ。それが無意味だといっているのではない。無論、それには意味がある。我々はそれに頼ることで、生き延びることが出来る。 それは我々が「生きてゆくための能力」なのだ。そうした要請から認識能力があるのだとすれば、認識が正しく世界自身である必要など、どこにもない。 我々はそうして生きているだけなのだ、とわたしは思う。生きてゆくためにある認識能力の限られた範囲内で、自らを取り巻く世界のすべてを知ろうなど、傲慢不遜も甚だしい。それはたぶん目的の違うツールなのである。 だから、我々に確実に言い得るのはせいぜいが、「そこになにかある」という程度のことなのだ。 我々自身が、我々自身でないものと認識するなにものかがそこにある、としか、人間には言い得ないのだと思う。 そして、実は、その全体こそが世界の真の姿なのだと思う。認識能力が切り分ける世界を真としないなら、我々は認識能力をプリズムのように考えて、その前後を全体として考えることが出来る。認識能力を「わきに置いておく」のだ。そうして捕らえた、認識され得ない全体としての世界こそが、我々に認識し得る唯一正確な世界像なのだろう。それはまちがいなく「そこにある」からである。 少なくとも我々自身が生きて、認識している間だけは。 我々の消えた後に残るのが「何」なのかは、それこそわたしなどにはとうてい知り得ない。そしてしかし、それこそが、おそらくは真に正しい「世界」そのものなのだろうと思う。 人を食った話ではある。 2002/09/25 |
all Text written by Kaikou.