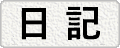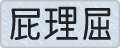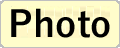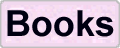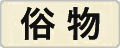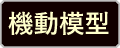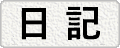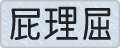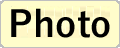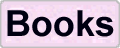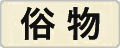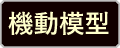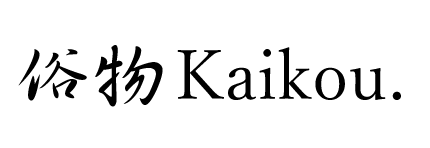|
夏の終わりになって、ヒグラシが鳴き、夕方の空を渡る風に冷たさが混じるようになると、赤く染まっていく光景を見ながら思うことがある。
この時間は、いつも同じだ。
去年の夏も、十年前の夏も、この光景はこのままだった。
きっとこの先も、私が生きて見る内は、このままだろう。
場所が違っても、見る風景は違っていても、夏の終わりの夕暮れは、時間がぼんやりしてしまったように、いつも同じ色をしている。
同じ時間、なのだ。
時間は常に流れ続け、ものも、人も、風景すらも変化し続けているというのに、夏の終わりの夕暮れだけは、常に変わらない。
そうは、思われないだろうか。
縁台の端に腰をかけ、わざわざ灰皿を持ち出して、煙草をくゆらせながらつらつらと眺めるに、夕暮れの光景は子供の頃に見たのとまるで同じで、自分だけが変化して、昔の場所に座っているような気に囚われる。
そう感じられることはないだろうか。
ヒグラシ達には時を止める力があるのかも知れない。
不思議な時間だ。
私はこうして幾重にも変わったというのに、空の匂いも、空気の温度も、まだ高い湿り気も、ヒグラシの音も変わらない。もはや浴衣を着て花火をすることもなく、西瓜をかじることもなくなった。それなのに、この時はどうだ、止まっているではないか。
なにも考えられなくなる。
日々のこだわりが抜け落ちてしまったように、ただ、ぼんやりと動かない時に身を任せる時間。
たゆたうこの時間はいつも貴重で、しかも、貴重だと気づかないうちに終わってしまう。それは、それだからこそ貴重なのかも知れない。あるいは、単に残酷なのかも知れない。
そして気がつくと夜の時間がやってきて、いつの間にか周囲の時計を進めている。
でも、今年はそれが貴重だと気がついたから、少し、得をしたような気がする。
夏が終わってゆく
(2002.Aug.16)
|