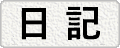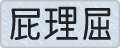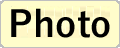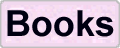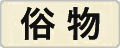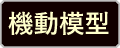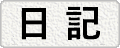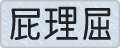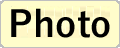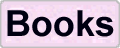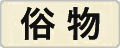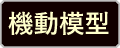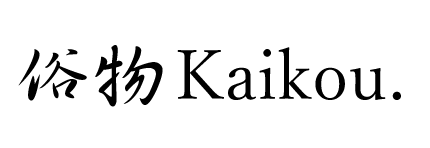|
二輪車に乗って生活するようになってから何年にもなる。(そういう仕事をしていた頃のお話です)
日中の大半を二輪車の上で過ごしているのだから、これはもう人間の生活とはいえない(文字通り、地に足がついていない)が、仕事だからしてやむを得ない。今日も地から足を離し、二輪車の上に座っている。街を走り、砂利道を走り、泥道を走り、濡れた毛布の上(あるのだ)を走り、畑の真ん中を走破し、再び街を走っている。そうして二輪車の上で暮らしていると(別段二輪車の上で寝食をしているわけではないが)、いろいろと見えてくるものがある。
一つには、人間がカラダで生きているのだな、ということがよくわかる。
なにを当たり前な、と思われるだろうが、存外現代人の日常生活では、これは忘れられているものである。
二輪車は体を使って走る。走るのは二輪車自体だが、それは体を使わないとたちまちひっくり返ってしまう厄介なシロモノである。体が、その感覚と動作を二輪車に合わせて操ってやらなければならない。体と機械を同調させて、今日もわたしは生きている。その、ただ生きている状態のためだけに、体を使わなくてはいけない。力を出して、というのとも違う。モノを持ち上げたり、押さえたり、といった単純な筋肉の使用ではなく、体全体が、重力と路面を感知して動かなければ二輪車はうまく走らない。
体が世界を感じ取って対応していかなければ、二輪車は走らないのだ(案外、二輪車に乗らぬ人には気づかれていないことかも知れない)。文字通り、体が世界を生きている。頭もそれは使っているが、この場合頭は体と同期していなければならない。体にそぐわぬ思考に気を取られては、二輪車はこれもたちまちコケるのである(まぁ実際のところ、十分に熟練すれば、走りながらの考え事は可能なのだが)。いずれ脳の一部は体と連動して動かなければ話にならない。無論のこと意識もである。頭が体を意識して、体が世界を意識して、機械と一緒に動く。二輪車に乗る者は皆そんな世界を生きている。そうしていると、電車に乗ったり、車に乗ったり、机に座っていたりする暮らしでは忘れてしまいがちな「身体性」を、これみよがしに思い出さないわけには行かない。なにしろ、ただ危険なく生きるためだけに、体の制御が必要なのである。その瞬間を安全に生きるだけで、体が機械を介して世界と同期している必要があるのだ。
機械を介して、というのは二輪車独特としても、かくそのようにして体が世界を生きていく感覚は、白状すればわたしの長らく忘れていた事である。わたしは二輪車に乗って日々暮らすことで、体が世界を生きていることを思い出したのだ。体と、そのリアルタイムな制御無しには、一瞬を生きることすら出来ない。ぐうたら生きていた頃には(あるのだ)、意識する必要の無かった感覚なのだ。
わたしは、体の制御無しでは一瞬も安全でない世界を生きている。それは裏を返せば、二輪車に乗ることが、体の緊迫した制御を必要とするほど危険であることをも示している。
実際、二輪車はただ走っているだけで運転者が危険な乗り物ではある。タイヤの状態やエンジン、ミッション、チェーンのコンディションにも拠るが、濡れた路面はもちろん、乾いた路面とて、二輪車が主に走る路肩には吹き寄せられた砂が載っていて、タイヤがロックせぬようブレーキを使わなければたちまち姿勢を崩す。それどころか路面状態によっては、ただ直進していてすら姿勢を崩すこともある。路は平坦などではなく、つねになんらかの歪みを含み、大型車のタイヤの多く通る位置は深くへこんでいたりする。田舎道に至っては路肩が斜めに落ちているところも少なくはない。砂利道や農道ならば、ギアやブレーキの操作を間違えれば余計な力が掛かってどこへ吹っ飛んでいくかわからない。そういった路面では強い力の変化を路面が吸収できず、路面の方が負けて滑り出すので、自動的にその上に載ったタイヤも、ひいてはバイクも(自分もだ)、ものの見事に滑ってゆく。
そうした操作に伴う危険ももちろんあるが、なにより二輪車に乗っていると、道路の危険さというヤツが身にしみてよくわかってくる。
二輪車乗りなら誰とを問わず周知のことだろうが、道路交通というものは、まるで奇跡のような神業のような、死と紙一重の危険が常に満ちているものなのだ。
道路はある。規則もある。それをほとんどの人が守ってもいる。
それでも、路上は危険の渦である。規則は正確に守られているのではなく、「微妙に」守られているからだ。また道路自体も、かならずしも安全だけを目指して作られているわけではない。まぁ、それを責めようと言う気はない。
路上という、限られた空間を、日々数千台のクルマが往来するのだ。
規則に則ってさえ、そりゃあどこかでミスは生じる。人間、まるで完璧とは行かぬ。まして何処の誰かもわからぬ、気性も感覚もまちまちな人々がクルマという凶器を高速で乗り入れ、入れ替わり立ち替わり過ぎ去ってゆくのである。気の迷い勘違い、不注意勘気魔が差した、と、ミスの元には事欠かぬ。
道路はニアミスの天国といっても、そう過言ではないだろう。交通量の多い道路はもちろん、人通りのほとんどない砂利道や農道といえど、人通りが少ない故に注意して走るクルマは少なく、ふいに危険に遭うことも多い。二輪車に乗って暮らしていると、死にかけることは二度や三度の話ではない。まして日々急ぎの仕事で走っているのだ。わたしを含めて、二輪車乗りや自動車乗りが道路で死なずに済んでいるのは、単に奇跡だといったとしても、これまた決して過言ではない。またもちろん、わたしの乗る二輪車自体も、歩く人々にとっては危険な凶器以外の何物でもない。わたしは、人を殺せる凶器を駆って日々暮らしている。その歩行者達自身も、別段常にクルマを意識して歩いているわけではないらしく、双方ともに、危険な瞬間を作り合って生きているけれども。
だが、それはこの世の本質を教えてくれる。二輪車、クルマ、歩行者に限った話ではない。
この世は、危険に満ちているのだ。元来、そうしたものなのである。
精神的・経済的な危険という意味ではなく、文字通り命の危険だ。
人は、いつ、どこで死んだっておかしくはない。二輪車に乗って暮らしていると、そのコトが慣れた日常の奥から日々ほの見えてくる。わたしのような暮らしをしていなくとも、だから安全というわけではない。路を歩けば、そこには死が何処にでも転がっている。最近では、電車の中にさえ転がっているくらいだ。
しかしそれは、物騒な世の中になったと眉をひそめるべきコトではないのだ。
死は、元来が何処にでもあるものなのである。人は、脆い。
一瞬、ほんの一瞬の判断で死が訪れることもある。あるいはなにかの偶然で死に出会うこともあるだろう。気づかないだけだ。あるいは、見えないふりをしているだけだ。世界は、人に親切ではない。
そうして危険な路上を日々ぶいんぶいんと(静粛なマシンではないので)走っていると、また見えてくるものがある。
人々がいかに、多種多様な価値観と判断の中を生きているかということだ。中には独自の規則の中を生きている御仁もあらせられて、時には開いた口がふさがらない。
道路上には、そうした群像がいっぱいだ。周囲を見ない人、格好付けることに命を(ついでに他人の命をも)賭ける人、他人は避けてくれるものと思っている人、あるいは他人は常に危険だと思っている人、まるで路上を走る人々は、自分の知る規則が、この世のすべての他人にも通じていると思っているかのようだ。
お生憎である。つれづれに見る限り、この世の人々は、すべてが独自の規則と判断によって生きている。誰にでも通じる規則など、ない。ある人は他者の多くは常に慎重で冷静な判断を「してくれる」と思い、ある人は他者の多くは常に無謀で危険に「違いない」と思い、ある人はなにも考えていない。(ついでに言えば、そしてすべての人々は「世の中はなっとらん」と思っているらしい。なるほど、それだけは万人に共通の規則かも知れぬ)
人々は無論判断して行動する。右折、左折、減速加速に一時停止、乗り入れ乗り出し、あらあんなところに新しい店が(急減速)。だが、みんな同様の判断をしているわけではないのだ。
二輪車上から見る世の人々は、実に様々な価値観に基づいて運転し、行動し、道路を歩く。単に様々な人がいるというだけではない。ある時は親切に道を譲った人が、次には猛加速で走り抜けたりする。同じ一人の人間にさえ、ときに様々な規則が同居している。
たぶん、それが人間社会の本質なのだ。表面上、みなが同じように行動して見えるのは、無数の円の部分集合が大きいようなものなのである。だがすべての円は、決して重なることはない。数限りない人々が、独自の規則で自分を律し、他人に期待し、道路へと凶器を駆って乗り出している。二輪車の上からは、そうしたことがよく見える。前段の危険性にも通じる姿だ。
結局のところ、世界は生き物にとって過酷なのである。まして人間においておや。獣の爪の一ひねりで死ぬような生き物に、この世が安楽であるはずがない。
体を使って世界に同調し、機敏に、周到に生きなくては、たちまちの内に死ぬこともある。人ならぬ自然だけではない。そうした過酷な世界の影響を和らげるはずの人間社会もまた、数限りない勘違いの集積した、てんでばらばらなアメーバのようなものである(コワイ考えになってしまった)。
人の世を生きるのでさえ、ちっとも楽でも安全でもない。そら、あの交差点を渡る膨大な人波が、みな違う価値観と規則で動いているように、いつ振り返った顔が鬼になり、あるいは牙を剥くやも知れぬ。あるいは仏の顔を見せるかも知れぬ。ちっともさっぱり、予想は付かぬ。
人も、自然も、安全とか、楽とか、そうしたものとは違う原理で動いている。そうしたものは、体を使い、頭を使い、体を動かして、頭を絞ってようよう、少しばかりを勝ちとる類のものなのである。なにもしないでは死の危険に満ちた、だるい眠いでは済まされない力の荒れ狂う場が、(残念なことに)世界の姿だ。
気を抜けば怪我を負い、あるいは死に、あるいは他者に殺される(殺す方にそんな気があるかどうかは関係がない)。まことに、世界とは過酷なものに他ならぬ。少なくとも、毛皮も強い爪もなく、強靱な外骨格も栄養を蓄える房もなく、光合成も叶わぬ弱気な「こころ」を持つ生き物には、世は過酷以外のなにものでもない。
とはいえ、困ってばかりもいられない。黙って死んでもいられない。今日もその過酷な世界に乗り出さなければ、今夜の食事が危ぶまれる。生きていかないわけにも行かぬ。
だから我々人間は、体を常にアクティブにして世界を感じ、重力に、気配に、感覚に同調し、頭を使って考え、判断し、最適と思われる行動を取り(実際にそれが最適であるかどうか、その自信が持てないのは人間の負った最大の不幸であろうし、また人の考える最適など、所詮は足りない物差しで測った数値なのだが)、過酷な世界をあるいはかわし、あるいは切り開き、あるいは押しのけて、あるいは息を潜めて身を隠し、あるいは迂遠に、生きていく他はなにもできない。
体で感じ、頭で考え、体で動いて生きていく。
人間とは、他のすべての生き物がそうであるように、またそうしたものなのだなぁと、当たり前の、しかし忘れ去っていたことが、二輪車の上からは見えるのである。
そしてわたしは今日もキック・スターターを蹴り飛ばし、ブレーキを踏んで足をつき、車体を振り回してアクセルを開ける。
こう書くとイヤな話のようだが、なに、そればかりでもない。
二輪車の上で暮らすのは、たとえ危険に満ちていても、過酷な世界の姿を目の当たりにすることにはなっても、時に恩恵もある。
二輪車というのは普通単騎である。まして配達バイクでは二人乗りどころではない。そして、電車に乗る人や、通行人とは「異なる速度で」動いている(郵便屋はさらに通常より異なるチョコマカした速度で動いている)。まったく動き続けているわけでもないし、止まってもいない。そして、流れる世界の中心にいるのは、自分一人、なのである。
おわかりいただけるだろうか。わたしは日々、危険に満ちている中で、世界とゆるやかに切り離され、この世の不思議な姿を見ている。流れてゆく世界だ。
二輪車乗りは静止した世界に生きてはいない。常に動いているわけでもない。そしてその動く世界を制御しているのは、常に(冒頭に述べたように)自分の体、なのである。これは他の世界に暮らすどの人とも違う日常である。安定して座っているわけでもない。常に重力と、タイヤと、路面とバランスをとっている。動き、そして体そのものは座っている。感覚はせわしなく働いて、体の制御をしているが、腕を振り回すわけでも、足を動かすわけでもない。重力は常にその方向を変えるが、体そのものは動いていない。といって安定してもいない。
世界は高速に流れてゆき、時折止まるが、自分の体はゆるやかにバランスをとっているだけである。二輪車の走行感覚は、馬とも、クルマとも違うのだ。
日がな一日その不思議な運動感覚の中に生きていると、不思議な世界が見えてくる。
ある場所は騒がしい。在る場所は人が多く、在る場所は静かで、人がいない。生活の場に踏み込むこともあれば、無人の廃墟も過ぎてゆく。ある林道は自然をそのまま残している。在る場所は喧嘩腰にクルマ達が争っている。
不思議な運動感覚のまま、水田を過ぎ、住宅地を(チョコマカと)疾駆し、農家に入る。そして出る。そうして眺める世界は、ゆるやかに自分から切り離されている。緩やかに繋がったまま、たしかに違う速度域の中にある。そして、(郵便屋は)そのどれにも関わり、どれとも関わらない。一日走ると、街の全体像がおぼろに見えてくることになる。
ふと、人気の少ない静かな場所に二輪車を止める(サボっていると言われるので)。ここから表現が唐突になるのでご勘弁願いたい。
世界は美しい。
この世界は、確かに美しいのだ。
二輪車に乗って暮らしていなければ、あの奇妙な速度域の中に、あの奇妙な運動感覚の中にいなければ、「こんな風景は見えなかった」のだ。
動き、止まり、動き、止まる。世界は流れ去っていく。でも、止まる。わたしは座っているが、止まってはいない。動いてもいない。だが、体はバランスをとっている。ゆるやかに切り離されて、わたしは世界を見ている。
この世界は美しい。
愛おしいかどうかは、断言できない。そうと言い切るには、二輪車乗りは過酷なものを見過ぎている。だが、ふと風景の中に停止するとき、見知らなかった世界の姿を実感できる。
確かに過酷ではあるのかも知れない。確かに危険に満ちてはいるのかも知れない。気が違ったように、長さの違う物差しを持った無数の人々が右往左往しているかも知れない。それでも、
この世は美しいのだ、皆々様。
二輪車に乗って暮らすのは、そうでない人々とは違う世界を生きることである。流れ去り、止まる世界。関わりを持ち、同時に関わりを持たない世界。他のすべての人々と違う速度域の中で、他のすべての人々と違う身体感覚の中で日々の暮らしを送ることで、わたしは流れの違う世界の姿を見る。
時間が一定だ、などと言ったのは、どこの大莫迦者だろう?
きっと二輪車に乗ったことがないのだろう。
二輪車の上から見える世界は、危険に満ちていて身体的であり、過酷だが、速度域のすべてを含み、すべての風景を含み、多種多様な人々の光景を同時に含む。それらは同時に全体であり、流れる二輪車の風の中に同化している。二輪車の上からは、日常見えるそれとは違う世界が見えるのである。違う速度域の中から(マシンがマシンなのでそう高速ではないが)世界の風景を見ることがおありだろうか?
わたしは毎日、日がな一日見ている。クルマの、四輪車の中からは見えぬ光景である。あれは人の感覚を重力から切り離し、世界から断ち切ってしまう。なにもしなくとも(体が緊張しなくとも)倒れたりはしない。だが二輪車では、世界とはゆるやかに切り離されるのだ。命の危険を伴いながら。身体感覚を総動員しながら、しかも動かずに、世界の方が流れていく。ときに止まる。そうして現れる世界は、美しいのである。
人が無数に生きている。それに一瞬関わり、離れていく。動物が生きている。虫も生きている。植物も生きている。生きていないと言われるもの達も大量にある。道路の脇を流れ去ってゆく。わたしは体で世界を感じ、同時に流れ去っている。いや世界の方が流れ去ってゆく。どちらでもよろしい。
二輪車の上で暮らすのは、流れる世界の上で暮らすことだ。そこは人間の感覚がついていけないほど速く流れてはいないし、止まってもいない。不思議な世界だ。(郵便配達独特の走行感覚であるのを考慮したとしても、多かれ少なかれ二輪車からはこういう世界が見える)
そんな世界は、普通見えまい。
そして、そんな「流れ行く世界」とわたしを媒介するものは、機械なのである。電子機器は一つも搭載されていない。からくりというほど単純でもない。人間無しではまっすぐ動くさえままならない、仕方のない機械だ。サイズも小さい。重すぎもしない。といって舐めてかかると死の危険を秘めている。機械は人の意に従ったりはしない。操作に従うのみである。小さな動力機から力を出して地を蹴り、重力と釣り合いをとるのは人間に任せてただ走り、曲がる。その力は小さいが、操作によっては獣をも越える力を人にもたらしてくれる。うまくやれば、山道だってなんのそのだ(余談だが、わたしはこういうなんの特徴もない二輪車で山道を走破するのが得意である)。
コイツは割と愛おしい。
あまり趣味の良いとはいえない赤に塗りたくられた二輪車だが、つもった雪をエンジンで(泥よけではなく)かき分けて雪道を走破したのには恐れ入った。なんという機械だろうか。(ちなみに、二輪用のチェーンを装着している)
機械と人が共生しているのは現代の世の常だが、なかなか信頼の置ける相方なのだ、二輪車というのは(ウチのクルマだけかも知れないが)。大型の獣並の力を与えてくれるが、一人で放っておくとすっころんでしまう。
さほど維持費もかからないし、必要十分な力を出す良い機械なのだ、二輪車は。
要するに、わたしはこの赤い機械が気に入っているのである。気に入った機械とともに、本来出し得ないはずの力をだして世界を生きるのは、他の動物にはない人間の特権である。しかも滅多にあるものではない(あなたは、気に入った機械と生きておいでだろうか?)。
そうしてわたしは二輪車の上で暮らし(寝食は共にしないが)、流れる世界を見、この世の過酷を思い、死の危険に身をさらし、今日も他の人々と違う速度域の中を生きている。
文中で二輪車、つってるのはHONDA・MD50(赤と白のおめでたい色で有名なアレ)のことでござんす
(2002/06/25)
|