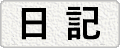
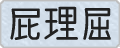
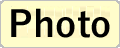


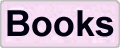

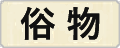
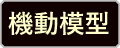



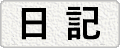
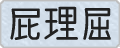
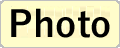


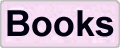

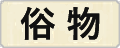
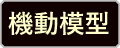




復活! 魔人VEpisode.2 ケニー・ロビンソン ケニー・ロビンソンはすぐアメリカに帰りたいとは思っていなかったが、日本に住み続けたいとも思っていなかった。 お父さんの海外赴任で一家を挙げて越して来てから半年たつが、会うのはユニバーサル・ジュニア・スクールの同級生達だけで、日本人の友達はいなかったし、いまだに日本語はちんぷんかんぷんだった。 日本には野球やサッカーをするところが少なかったし、レジャー施設は遠くて混んでいて、映画館も少なかったから、遊びといっては、友達の家でゲームをするくらいしかなかった。だから、日本人の子供達ほどテレビゲームに熱中しているわけではなかったが、お父さんが新しいゲーム機を買ってくれないのは気に入らなかった。 友達のコリンは少し前のゲーム機を持っていて、それが仲間達の持っている最高のゲーム機だったので、新しいゲーム機を手に入れれば、ケニーがテレビゲームをする際の主役になれるはずなのだ。だがクリスマス・プレゼントにも、誕生日にも、もらったのは分厚い本と野球のグローブだけで、野球をする場所もなく(あってもそこは日本の子供達で一杯で、入ってゆきづらかった)、本を読む習慣のないケニーにはそれが不満に思われてならない。 学校の勉強が遅れないようにしろというお父さんの口癖も、後かたづけをヒステリーのように指示するお母さんの口にもうんざりだった。お父さんとお母さんがちっとも仲良く見えないのにもうんざりだった。 お母さんの次から次へと話す隣人や友達の家の噂話にも飽き飽きだったので、ケニーはよく友達の家を次々と短時間で渡り歩いてはいろいろの遊びをした。サッカーは難しいので、ジェイナスの家の、日本の他の家から見ればはるかに大きな、しかし広いとはいえない庭でミニサッカーをし、ジョンソンの家ではゲームの塔を倒して遊んだ。アンジェリカと遊ぶと女の子の服を着せられるのであまり遊ばなかった。 一度家に帰ったとき、お父さんがむっつりと歩き回っていて、お母さんが泣いていたときには、もうこんな家に帰りたくなかった。 そんな時ケニーは日本の街を流して歩いた。 言葉は一つもわからなかった。ごちゃごちゃした電線だらけの街の、唯一歩ける通りを、騒々しいパティンコと変な言葉が書かれた看板やひっきりなしに人が出入りするコンビニエンス・ストアを眺め、覗きながら誰にも話しかけられないように歩いた。 アメリカ人に会うことは希だったが、時折友達や、学校で顔を見たことのある外国人の他にも外国人が歩いているのを見た。ここへ来るまでケニーは知らなかったことだが、日本の街には白人も、黒人も、スペイン人もアラビア人も、日本人とは少し違う調子でしゃべる中国人もいた。数は少なかったけれどたいていは旅行者か学生で、出稼ぎに来ていると話しているのを小耳に挟んだこともあった。 たいていの外国人達は、落ち着き無くふらふらと、あるいはわざと声高に喋りながら歩いていて、周囲からくっきりと浮いていたのですぐにわかった。だから、その男を見かけた時には不思議な気がした。 その白人は、日本の街からちっとも浮き上がっていなかった。コットンの半袖のシャツを着て、色の薄くなったジーンズをはき、ゆったりと、周囲を眺めたり前をじっと見たりしながら、にこにこと歩いていたのを見かけたのが最初だ。ものすごく大きかった。背の高い電柱の半分くらいあるのではないかと、ケニーは思った。むろんそんなに背が高いはずはなかったのだが。 上背があって、肩幅が広く、腕も脚も筋肉でぱんぱんにふくらんでいた。それでも怖い感じはしなかった。 子供のようににこにこした顔と、ゆったりした余裕のある動作のためだった。頑丈そうな顎を開いて、片言の日本語を喋り、商店の中年婦人や物売りのおじさんと親しげに話しているのを見たのが最初だった。 彼はじっとみつめるケニーに気が付くと、鷹揚な動作で大きな片手を挙げ、にこやかにハーイ、と言った。 ケニーはあいまいに挨拶を返して、その時はすぐ帰ったが、しばらくして両親が学校を変われと言い出したのに腹を立てて家を飛び出したときに、繁華街の中央で再び見かけた。 今度は彼は、仕事仲間らしい日本人の労務者達の間で、缶ビールを両手におどけていた。 作業着を着て、奇妙に手足を振り回して、舌を出し、なにか片言の冗談を言っては周りの者を笑わせていた。変なおじさんだ、と思ってケニーは足早に通り過ぎようとしたが、こともあろうに彼は涙を拭いて過ぎ去るケニーの後を追ってきた。BOY、どうした、と彼は陽気な声で言った。 お父さんと喧嘩をしたのか? 心配ない。きっとわかってくれる。お母さんとも喧嘩をしたのか? 心配ない。きっと君のことを思って怒っているんだ。よく話を聞いて、いいたいことを言いなさい。 そして彼は、陽気に妙なことを言った。 「ダイ、ジョー、ブイ!」 そしてげらげらと笑った。 ケニーは酔っぱらいだと思って、足早にその場を去った。彼はその後ろから、迷わないうちに家に帰りなさい、と声をかけた。 果たしてケニーは道に迷い、日本の警官に案内されて家に帰ったが、そのことを恥じて両親に当たり散らしているうちに、学校を変わる話はうやむやになった。 次に見かけたときは、ケニーが友達に嘘の自慢をしているときだった。自慢話は際限が無く進んでしまい、嘘だと言い出せなくなった頃、大人達の喧嘩が子供達の目を引きつけた。ケニーの嘘の自慢はうやむやになった。 喧嘩の輪の中心には、あの大きな白人がいた。桃色のゴルフシャツを着て、丈夫そうな綿のズボンをはき、殺気立った大人達の中心にすっくと立っていた。厳しい顔であたりを見回し、ジョウダンハ、ポイポイネー、と言ってにやりと笑っていた。喧嘩が始まっても、彼は誰も殴らなかった。殴りかかってくるのを止め、脚を払い、怖い顔で脅かして突き飛ばしただけだった。ぶつ切りの英語で、止まれ、家族を思い出せ、と言い、落ちていたバッグを拾って小さな老婦人に返した。君たちは、良くない。それ以上やると、と彼は言って、すごい顔で脅して見せた。大人達が逃げ出して、その場が収まったとき、子供達は興奮しておしゃべりに熱中し、ケニーの嘘の自慢のことは忘れられた。ただ一人、まだ小さなサイモンが覚えていたが、ケニーは睨んで黙らせた。大男のことを、ケニーより年上のホークは、悪いヤツは殴らなくちゃいけないのに殴らなかった。あれでは悪いヤツは改心しない、と言い、サマンサは平和的でとても素敵だ、と言った。ケニーにはどうでもよかった。嘘がばれなかったのがなによりだった。 やがてケニーは家の物を持ち出して遊ぶようになった。お父さんの時計はよい玩具になり、お母さんのバッグは女の子達の物を入れておくのに好都合だった。お父さんとお母さんがびっくりするのも面白かった。両親はそのことをひどく怒って、親子は喧嘩をするようになったが、ケニーは父親に殴られたのが気に入らず、家ではずっと黙っていた。お母さんは金切り声を上げるようにしてケニーに話しかけ続けたが、ケニーはぶっきらぼうに返事をするばかりになった。お父さんは息子同様黙りがちになり、夫婦の寝室からは夜半に喧嘩の声がするようになった。 ケニーは自分が悪い子になったことを知っていたが、治すことは出来なかった。どうしてそうなるのだろう、とケニーは考えた。そもそも、どうしてこうなったのだろう? 日本に住むようになったからだろうか? そうかもしれない。親たちがなにも買ってくれないからだろうか? そうかもしれない。お父さんはケニーの望むようには行動してくれなかった。お母さんが金切り声ばかり上げているからだろうか? そうかもしれない。家の中はケニーには居心地の良い場所ではなかった。なんど考えても、ケニーには結論は出なかった。 その頃、少し遠い街に新しくできたレジャーランドで、ジュニア・スクールの子供が一人、行方不明になる事件が起きた。 まだ入り立てのメキシコ人の少年が、レジャーランドで両親と遊んでいるうちにに行方不明になり、帰ってこなかったのだ。 ケニーのお父さんとお母さんは駐留外国人達のグループの中心にいて、ケニーや他の子供達をつれて周囲を探して回ったりしたが、少年は見つからなかった。誘拐の線も考えられたので、日本の警察官達とレジャーランドの近くで話し合いを持ったりしていた。この時ばかりは、両親も、ケニーもおとなしく協力して少年を捜し回った。 少年は見つからなかったが、その代わりにケニーはレジャーランドのすぐそばであの白人を見かけた。 彼は太い腕を組み、難しい顔でレジャーランドの巨大な遊具の群を見上げていた。怖い目をしていたので、ケニーは両親にそのことを教え、警官達が彼に質問をしたが、自分も話を聞いて少年を捜しに来たのだと答えたと、ケニーはお父さんから聞いた。 そのことがあってしばらくしてから、ケニーのお父さんは休暇を取ってレジャーランドへ一家で遊びに行く提案をした。少年の身は心配だが、あそこへはまだ遊びに行ったことがないから休日を過ごそう、というのだった。 ケニーにはよく理解できなかったが、遊びに行けるぶんには異存無かった。 ある初夏の朝、一家は車で出かけた。 レジャーランドのアトラクションは面白かった! ケニーは買い食いをし、ジェット・コースターのような列車に乗って地底を巡り、あるいは立体映像の映る眼鏡をかけて光線銃を振り回し、立体映像の怪物達を倒して遊んだ。途中、通りを歩いていると 「....Magic,The Child have a Great Magic Power(魔力だ。この子は魔力を持っている)...」 という声が聞こえたような気がしたが、たぶん空耳だった。あるいはアトラクションのナレーションだろう。 ポップコーンを買っているとき、なんとまたあの白人を見かけた。アリナミン、と書かれたドリンク剤の箱を抱え、一本取りだして旨そうに飲んでいた。ケニーを見つけると、陽気な顔でドリンク剤の瓶を持ち上げ、爽やかに笑った。 バカじゃないだろうか、とケニーは思った。 ケニーが両親の元に戻ると、二人は喧嘩をしていた。 理由はよくわからなかったが、よく聞いてみるとあれやこれやいろいろありすぎて、さらにわからなくなった。 両親はいったん互いの矛を納めたが、揃ってぷんぷんしたままケニーの手を引き、「地下迷宮の冒険」なるアトラクションに乗り込んだ。 レジャーランドの地下にわざわざコンクリートの迷宮を作り、暗くして、仕掛けとテーマと、客が参加して乗り越えるべきイベントを用意したゲームだった。英語のコースも用意されていたので、ケニーと両親は他の外国人達と一緒にまとまって英語のコースを選択した。 客達は十何人かづつのチームにまとめられ、次々と迷宮に乗り込んでゆき、アナウンスの解説を聞いて、パズルを解いたり玩具の銃を手にとったりして、課された障害を乗り越えてゆくのだった。 他の客達はおおいに興奮し、嬌声をあげてなんやかやと協力したり、討論したりして楽しんでいたが、ケニーの両親は少々がたぴししていて、少々気まずく遊んでいた。ケニーはそれがとても恥ずかしくて、わざと大きな声を挙げてゲームに参加し、お父さんとお母さんに声をかけ続けたが、反応は芳しくなかったので、心の中で怒り始めた。 どうして僕はこんなお父さんとお母さんの元に生まれてきてしまったのだろう? どうしてほかのみんなのように幸せになれないのだろう? せめて、どうして友達(日本に来る前の友達のことだ)のいるアーカンソーで暮らせないのだろう? こんな家族でなければよかったのに。 こんな生活でなければよかったのに。 みんないなくなっちゃえばいいのに。 その時、暗いコンクリートの洞窟の壁に、ほんの短い間、赤い炎が這い回ったのをケニーは見た。天井に隠して設置された蛍光灯がまたたいた。 だがそれはすぐに消えてしまったので、他の客達も、ケニーの両親も気づかなかった。アトラクションは進んでいった。集団でぞろぞろと、迷宮の地下へ、地下へと進んでゆく。こりゃあ帰りは登りがきつそうだな、と誰かが言った。なんでそんなことを気にするんだろう、とケニーは腹を立てた。ゲームに集中すればいいじゃないか。 暗い迷宮全体が歪み、ゆらめいたような気がケニーにはした。ケニーはめまいがおきたのかと思い、頭を抱えてうずくまった。気分は悪くなかった。ただ無性に腹が立っていた。お母さんが心配して声をかけたが、ケニーは、大丈夫だよ! なんでもないよ! ときつく叫んで答えた。 やがて一行は真っ直ぐに続く通路へ出た。そこも暗く、照明が明るくなったり、暗くなったりしていた。客の一人が不安そうに天井を見上げ、おいおい大丈夫かい、なんだか天井が崩れてきそうな雰囲気じゃないか。そう言って冗談めかして笑った。 その瞬間だった。 突然、通路の床がいっせいに青黒い液体に変わり、客達がみな床の下へ落ちた。たくさんの悲鳴が上がったが、すぐには止まず、はるか下の方まで落ちていった。 ケニーは固い泥のようなものに腰を打ち付けて落ち、たぶん他のみんなより大きな悲鳴を上げた。顔を上げると、真っ暗な目の前に薄い青色の、ぬめぬめした物体が浮かんでいた。物体には一つ目があって、小さな口を開けて笑った。 ケニーはさっきより大きな悲鳴を上げた。 手を付いて逃げようとして、床がぬるぬるしているのに気づいた。脚が滑るのを我慢して、ケニーは手近な方へと逃げ出した。 お父さんとお母さんの名を呼んだ。何度も呼んで、幾度も暗い壁にぶつかり、泣きながら走っている内に、お父さんの声が聞こえた。 ケニーは角を曲がってお父さんを見つけ、ぶつかっていった。気が付くと近くにお母さんもいて、ケニーはようやく人心地つくことができた。 いったいどうなっているんだ、とお父さんは喚いた。事故か? 係員はどうした? 他のみんなはどこにいるんだ! だがいくら呼ばわっても、誰も現れず、係員も来なかった。 ケニー達は仕方なく、泣き始めたお母さんを伴って真っ暗な、今度は本当の迷路を歩き始めた。 なにが起きたのかわからなかった。人工の地下の迷路から、さらに地下へ落ちたはずだったが、ごつごつして曲がりくねった、岩が剥き出しの迷路は生暖かく、まるでどこかから暖房が洩れているようだった。壁はぬるぬるしていて、気持ち悪い変な色の苔がびっしりと生えていた。 時折、なにか得体の知れない物が足下を走り抜けて、その度にケニー達に悲鳴を上げさせた。やがて泣きやんだお母さんは、こんなところに来なければ良かった、と愚痴をこぼし始めた。愚痴は際限なく続き、終いには日本に来たこと、ケニーの振る舞いが悪くなったことにまで及んだ。 日本に来たのは間違いだった、という意見にはケニーも賛成だったが、なにもこんな時にこんなところで、しかも自分のことまで言わなくてもいいじゃないかと、ケニーはまた腹を立て始めた。 お父さんは最初黙って聞いていたが、やがてかんしゃくを爆発させて、うるさい! 黙れ! とお母さんをどやしつけた。ケニーはもうイヤになって、両親の元を走り出し、勝手に次の角を曲がった。 そこに怪物がいた。ぬらりと足の長い、円い胴体だけのような毛深く醜い生き物だった。足の付け根の上に口があった。よだれを垂らしながら口を開けた。 ケニーは悲鳴を上げるのも忘れて脱兎のごとく駆け戻った。駆け戻ってから、意味のない声をあげて喚きに喚いた。両親は怪物を見て硬直していた。怪物は三人の前まで来ると、いやらしい口を開けて、 この子だ。この子だ。あとは邪魔だな。どうしよう。 と英語でゆっくりと言った。ケニーは恐怖で首を振り続けた。食べるのだろうか、とケニーは思った。一瞬だけ、食べるのならお父さんとお母さんが先だよね、と心に思った。 怪物は目のない胴体を曲げてケニーをじっと見るようにして、奇妙な笑い声を挙げた。そして言った。 そうか、両親が邪魔なのか。 ケニーはどきっとした。なにをいっているんだろう? 僕のことだろうか? どうしてわかったんだろう? ケニーがそう思った瞬間、怪物はお父さんとお母さんに飛びかかり、二人いっぺんに食べてしまった。ものを噛むイヤな音がした。 ケニーはこれ以上には上げられないような悲鳴を上げた。頭を抱えてうずくまった。なにか怖ろしい夢を見ているような気がした。力一杯に喚いて、頭を振り、そっと後ろを振り返ったとき、怪物はそこにまだ立っていた。 ケニーは声が出なくなった。 お父さんとお母さんをどうしたの? と怪物に聞いていた。 お前が望んでいたから、食ってやった、と怪物はゆっくり答えた。 ケニーは心臓が止まりそうになり、何度も、何度も、何度も、頭を強く振って怪物を追い払おうとした。怪物は消えなかった。 望んでない! そんなこと望んでない! ケニーは大声で叫んだ。怪物は笑った。 嘘だ。おまえの心にそう書いてあった。おまえはそれを望んでいた。 望んでなんかいない! ケニーはなおも強く叫んだが、怪物は大笑いするだけだった。強い足音が聞こえた。怪物は言った。 望んでいたとも! そして我々は、おまえが望みだ。 怪物の背から、それまで見えなかった二本の尻尾のようなものが伸びて、ケニーを絡み取った。そのままケニーは怪物の頭の上に持ち上げられた。 怪物は脱兎のごとく走り出した。ケニーの目に真っ黒な天井が流れてゆくのが見えた。 怪物が走る向きを変えた。 すると急に速度が鈍り、やがてぼこんという妙な音がした。ケニーは地に落ちて転がった。 ケニーは何がなんだかわからずに、手を付いて上体を持ち上げた。そこを、太い腕がすくい上げた。 ケニーは驚いて金切り声を上げそうになったが、腕の主を見て声が出なくなった。 ケニーは、あの白人の大男に抱え上げられていた。 厳つい顔が心配そうに言った。大丈夫か、と。 ケニーは弱々しく首を振った。躰が震え出すのがわかった。 大男はにっこりして、バカみたいな笑顔のまま、ダイ、ジョー、ブイ! と言った。 おじさんは誰? とケニーはささやくように言った。 大男はゆっくりと太い笑みを浮かべ、こう答えた。 「I'm Victor. (ヴィクトール)」 TOPページ(目次画面)に戻るには、あるいは別のコーナーへ行くには上部の各タブをクリックしてください。タブの見えない方はこちらメニュー(目次画面)へ戻るからどーぞ。 |
all Text written by @ Kaikou.
http://www.fides.dti.ne.jp/%7ekaikou/index.html